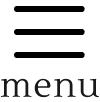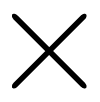コラム
2022/03/29
きっかけは割れ目

チョコレート好きな私にとって、疲れた時に口にするチョコレートは格別です。今回は私の大好きなチョコレートから広報TIPをご紹介します。
今回ご紹介するチョコレートは、オランダで大人気のチョコレートブランド、「トニーズ・チョコロンリー」です。
「あれ、でもなんだかいびつな割れ目。これじゃあ、均等に分けて食べられないじゃない!」と思ったあなた。
まさに、そこにトニーズが伝えたいことがありました。
世界のカカオ生産の約6割を占める西アフリカでは約156万人もの子どもたちが働いています。その結果、教育を受けられず、貧困の連鎖が生まれ続けているのです。しかし、一方で先進国の一部のチョコレートメーカーは低価格でチョコレートの原料となるカカオを買い続け、大きな利益を得ている。その先には安価な価格でチョコレートを楽しむ消費者が......
これこそ「いびつ」な世界じゃないのか! トニーズチョコからはそんな声が聞こえてきそうです。
トニーズチョコは、西アフリカの児童労働に問題意識を持ったオランダのジャーナリスト、ジャーナリスト トゥーン・ファン・デコーケンさんにより2005年に設立されました。チョコレート業界にはびこる奴隷制を終わらせることをミッションに、自らが使う素材はもちろん、カカオ、砂糖共にフェアトレード認証をを得たものを使用しています。
サステナビリティに関する話題は背景が複雑なことが多く、なかなか簡単に理解できることばかりではありません。それだけに、ついつい説明が億劫になったりしてしまうことも多いのではないでしょうか。しかし、消費者やステークホルダーとサステナビリティについてまずは話すこと、これは全ての始まりであり、とても大切です。
そこでおすすめしたいのが今回ご紹介したようなわかりやすい「コミュニケーションポイントをつくること」。人がふと気づくようなフックを意図的につくることによって、話を切り出しやすくしたり、見た方が気づきやすくすることが目的です。
もう一つ、コミュニケーションポイントの事例をご紹介します。
以前にご紹介した木造賃貸マンション(こちら)の玄関に設置された木製の棚。地元産木材で作られており、住んでいる方が地元産木材を意識したり、また、遊びに来られた方に「うちのマンションは地元産木材でつくられているんだよ」と話すきっかけにしてもらうために設置されていました。
確かに、部屋はごく一般的なワンルームマンションなのでこれがなければ、地元産木材で作られたマンションであることは忘れられてしまいそうですし、何もない中で、部屋に来た方に「このマンションはね...」と話すのもなかなか難しそうです。その意味ではとてもいい「コミュニケーションポイント」だと思いました。
児童労働も気候変動も生物多様性も、全ての社会問題はまず「知ること」から始まります。その「知る」きっかけとして、コミュニケーションポイントはとても重要です。コミュニケーションポイントを通してどんな情報を届けるか、どんな会話が生まれるか、考えてみるとワクワクしますね!
トニーズ・チョコロンリーについて詳しくはトニーズ・チョコ・ロンリー
おまけ、もう一つコミュニケーションポイントの事例をどうぞ(ステッカー)
2022/03/15
SNS発信とメディア掲載

今日は久しぶりに広報のコツのお話です。
メディアに取り上げて欲しい! 広報に携わっている人であれば誰もが思う願いですが、プレスリリースを出してもなかなか取り上げられないことも多いのではないでしょうか。もちろんコツを押さえたプレスリリースを作成し、戦略的に発信することは重要ですが、実は日頃のアクション、「SNSの発信」も重要です。
理由は二つ。
まず一つ目は、最近は自分でアカウントを持ち、ネタ探しをしている記者やメディア担当者が増えています。実際、私も、私個人、もしくは関わっている組織のSNSを見て、問い合わせをいただいたことが何度かあります。プレスリリースを出してもいないのに問い合わせをいただいてさらに記事や番組として取り上げていただけるというのはとてもありがたいお話です。メディア受けを狙う投稿を出す必要はありませんが、リーチしたいメディアの方が見ているかもしれない!と思って取り組むことをおすすめします。
もう一つは、日頃のSNSの発信が信頼につながる、という理由です。
メディアの方が日頃からSNSの発信を見ていてくださった場合、そこにある日、プレスリリースが届く。「あ、SNSで見たことのある◯○からのプレスリリースだ」。日頃からSNSで発信をしていれば、単なるプレスリリースではなく、よく知った組織のプレス、として受け止めてもらえます。SNSでの印象がよかったり、信頼度を上げるものであったりすればなおさらでしょう。
実際、取材の際に「いつもXXについて発信されていますよね」といったコメントをいただき、信頼してもらっていることを感じたことがあります。
一発ホームランも日頃の練習から。SNSの発信は地味に手間がかかるものではありますが、大々的なメディアカバレッジにつながる道と信じてぜひがんばってください!
2022/02/27
「ママ、男の子は強いんだよ」の背景にあるもの

「ママ、男の子は強いんだよ」。
これは、5歳の娘が最近ふと口にした言葉。聞けば女の子は弱いんだそうな。5歳でもうそんなステレオタイプになっちゃうなんて! 我が家は私の方が強いはずなんですが(笑)どうやら幼稚園で先生が、「女の子は弱いんだからいじめちゃだめ」といった趣旨のことを伝えている模様。いや、そもそも強くてもいじめちゃだめだし、「男の子は強くて女の子は弱い」なんて、男の子にとっても(強いと言われると弱みを表現しづらくなる)女の子にとっても(弱い存在であることが当然と思ってしまう)、将来にわたって感情や行動を束縛する呪文になってしまうのに。
これは参った、と思っていたところ、OECDの調査によると、男性女性像は5歳くらいまでにできあがってしまうのだそうです。つまり、うちの子は世界的な傾向にばっちり当てはまっている、ということが判明したのでした。
要因の一つとして私が気になったのが、この年頃の子どもたちが接するメディア「絵本」で描かれるジェンダーの偏りです。登場するのはお父さんよりもお母さんが多く、そのお母さんもエプロンつけて料理など家事をしている様子が描かれていることが少なくありません。エプロンをつけているの女性がダメ、というわけでは決してありませんがバランスが大事だと思います。家事や子育てをしているお父さんが描かれたストーリーもあるべきだし、さらに言えば、お父さんもお母さんも男性、もしくは女性であったり、多様な家族構成のファミリーが描かれていれば、子どもたちのジェンダーイメージはもっと自由になるのではないでしょうか。
生まれて5年で「男の子は強くて女の子は弱い」というイメージが定着してしまえば、果ては、世界経済フォーラム(WEF)が毎年発表する「ジェンダーギャップ指数2021」で120位代の常連、日本に直結するといっても過言ではないでしょう。SDGs目標5(ジェンダー平等を実現しよう)の達成もほど遠いものになってしまいます。
ジェンダー問題は解決策が見えづらいことから、SDGsの認識調査でも上位になかなかランクインしない項目ですが、発信する情報の工夫は比較的簡単で、ジェンダー問題の解決につながる大きな力になるのではないでしょうか。その意味では、商業写真を提供しているゲッティイメージズ ジャパンが、写真を通してジェンダーギャップを解消しようとしている取り組みにはなるほど!と思わされるものがありました(こちら)。
メディアが私たちのジェンダー認識の形成に与える影響は大きいもの。広報をしていく際にもしっかりと心がけていきたいものです。
*冒頭の写真は最近娘が描いた絵。左端が私、夫、娘。描かれた大きさにどきっ...笑。
2022/02/04
正直が一番!「青のり」に学ぶコミュニケーションの基本

【サスコミュラボ no.1 「正直が一番」】
すじ青のりが帰ってきました!
何の話かと言いますと、お好み焼きや焼きそばにかける「青のり」の話です。
1971年から『青のり』を販売してきた三島食品は2020年7月、原材料の変更を理由に、パッケージを青色から黄緑に、商品名を『青のり』から『あおのり』に変更しました。(詳しくはこちら/筆者執筆)
気候変動による海水温の上昇などを理由に原材料となるスジアオノリが激減。生産量のピークだった2015年と比較すると10分の1にまで減り、価格も高級肉並になってしまいました。
そこで、他の種類のノリでしばらく対応することに。その際、単に原材料名の表示を変えるだけではなく、パッケージの色まで変更し、名称表記もひらがなの「あおのり」に変えたのでした。見た目と香りが良いスジアオノリへのこだわりと消費者に確実に伝えたいという正直な思いから出た行動でした。
(右が変更前、左が変更後。三島食品ウェブサイトより)
この真摯な対応がSNS上で話題に。三島食品の「必ず帰ってきますから」という熱いメッセージの応えるかのように「待ってます!」というメッセージがあふれました。
それから約1年半。約束通り、養殖と天然ものを組み合わせたスジアオノリ100%で帰ってきた、というわけです。
ここから学ぶことは何でしょうか。私はやはり「正直が一番!」に尽きると思います。ちょうどこの記事を書いている2022年2月はじめ、アサリの産地偽装が話題になっています。報道をみているとかかわっている方々はどうやら承知の上で産地偽装をしていた模様。見た目だけで産地は分からないから大丈夫だろう、と思ってしまったのでしょう。産地偽装は食品表示法違反です。しかし、問題はそれだけにとどまりません。商品そのもの、商品を販売している店、つくっている会社への信頼失墜につながります。
今後、昨今の気候変動や環境変化によって原材料の変更を余儀なくされることも増えるでしょう。本来の質が保てない時もあるかもしれません。でも、そんな時は邪なことは考えず、正直に事実を伝えることが一番です。
今回の「青のり」のように、産地変更を積極的に伝えるコミュニケーションをとれば、ますますファンが増え、原材料変更という災難もブランド価値を高めるプラスの機会として活用することができます。
ということで今日のサスコミュラボのポイントは「正直が一番!」でした。
*サスコミュラボとは:サステナビリティを高めるためのコミュニケーションを調査研究するラボ
2022/01/27
人も森も海もハッピーに 地産木造ビル

富士リアルティ(株)・湘南乃工務店さんが藤沢駅近くに建てた湘南初木造ビル見学会に行ってきました。地域で木造ビル建築をすすめていくために必要なものとは何か、地産木造ビル推進本舗の市川宣広さんにお話をうかがいました。(前編はこちら)
●地域を動かすストーリー
地域で地元産材を使った木造ビルづくりをすすめるにあたって大事なものは、「ストーリー」だと市川さん。
たとえば今回の湘南の場合、湘南ビーチの汚れ(環境省水質判定B)を憂う湘南乃工務店さんの思いからはじまりました。「水源の森が適正に手入れされていないことが原因の一つではないか、であれば水源となる丹沢産の木を使うことで若い山々に生き返らせたい」。
江ノ島ビーチに注ぐ川の上流にある、森で育まれた丹沢の木を使用することで森が元気になり、川の水が浄化され、きれいな海ができる。木造ビルを普及していくことは、湘南の人たちがこよなく愛する海のためにもなる、というストーリー。
こうしたストーリーが、地域の人たちの心を動かし、普及の原動力になるというわけです。確かに、地域の林業、森を活性化させていく、といった場合、一部の人だけが関係して終わりがちですが、これなら関係人口も増大、賛同者が増えそうですね。
写真:ドアをあけてすぐ正面にあるモニュメント。焼印は神奈川県産木材マーク。これがあることで、このビルに地元産材が使われていることを住人に常に認識してもらえるコミュニケーションポイントになる。友達や家族が来た時にもきっとここをきかっけに話が弾むはず。
●地元産材は虫にも強い
地域の木材を使うメリットは、林業を元気にするだけではありません。地元産木材の使用は地域の気候風土にあっているので、腐ったり、虫(シロアリ)に食べられたりしにくいことが大学の実証実験で明らかになっているそうです。食べ物は身土不二が大事、と言われますが、住まいも同じなんですね。
さらに、今回のように地元の工務店が建設すれば、「経済的な地域循環だけではなく、災害時のレジリエンスも高まります。何かがあった時にはすぐにかけつけてくれますからね」。確かに。昨今、急増する自然災害を考えるとこういう点はますます重要になりそうです。
●木造建築物あるある質問!
木造建築物にあるあるな懸念も思い切ってぶつけてみました。
まずは耐久性。素人のイメージながら、なんとなく鉄筋の方が長持ちしそうな気がします。「いやいや、世界最古の木造建築物、法隆寺を思い出してください」。思えば約1300年以上の年月を経て、いまだに健在。「摩擦にも強いため、仏像にもよく使われています」
音は? 「音楽ホールを思い出してください。もともと吸音性は高い素材で、最近では技術によってさらに高められています」
燃えやすいのでは? 「実は木は燃えるのに時間がかかるので人を守る素材なんです。逆に鉄骨の場合、酸や火に弱く、一定の熱が貯まると崩れてしまい、中の人は危険です」
高い建物は難しいのでは? 「法隆寺の五重塔の高さは約32mとマンションの10階建てに相当します」
メンテのノウハウはあるんでしょうか? 「木造は歴史の長い工法なのでメンテ方法は確立されているんです」
言われてみれば確かに、と思うことばかり。質問を重ねるうちに、身近なところに答えはすでにあることに気付かされました。
国産材、とくに地域木材はさすがにコストが高くなるのでは?
「地元産材は平均的な国産材の1.7-1.8倍するのですが、今回の場合、地元産材を使うことによる全体コストは1-2%UPくらい。大幅なコストUPはありません」。1-2%UPなら、なんらか吸収できそうですね。
写真:インターフォンの周辺にも地元産材が使われており、よい香りに癒されました。来訪者にもよいイメージが伝わりそう。これもいいコミュニケーションポイントですね。
●カギは消費者の認識
今回のビルは投資家=オーナーが確定しており、すでに今後、何棟か建てることが決定しているそうです。背景にはやはり、昨今のSDGsへの関心の高まりがあるのだとか。「神奈川県や藤沢市など行政の注目度も高い」と市川さん。
いいことづくめで今後、木造ビルは急拡大しそうに思いましたが、今後の進展のカギとなるのは「消費者の理解」とのこと。不動産情報で低層の木造となると「木造アパート」と表記されることが多く(実はこのあたり、表記のルールは特にないそうです)、前述のような懸念、ネガティブなイメージを持たれがち。選ばれなければせっかくの取り組みが後退しかねません。
消費者の「木造」に対する認識を変えていくこと。木造ビルを選んでもらうことによって、地域の山、林業が元気になり、自然が守られ、地域でお金がまわる。「そんな好循環をつくっていきたい」。市川さんの言葉に力がこもっていました。
人も森も海もハッピーにする。
木造ビルがつくりだす地域社会の幸せな未来に期待感が高まりました。